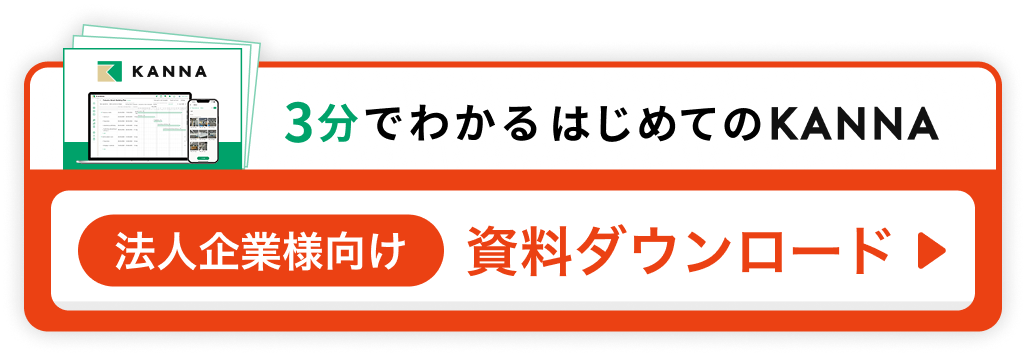製造業のExcel工程管理から脱却、若手もベテランも使いこなす現場のデジタル化と意識改革

��レジャー用途だけでなく、移動式オフィスや災害時の避難拠点としても需要拡大を続けるキャンピングカー。その製造販売を専門に手掛ける日本特種ボディー株式会社は、高い安全性とお客様一人ひとりのニーズに応えるカスタマイズ性を強みに成長を続けています。
しかし、その成長の裏側で、製造現場にはあまりに複雑で煩雑な工程管理という課題が横たわっていました。Excelの表では顧客ごとに異なる仕様を管理しきれず、更新に時間を取られ、「工程表を見ても最新情報とは限らない」という現場の疑念から口頭伝達に頼り、「言った、言わない」の温床になっていたと言います。
そうした状況を打開するため、同社はKANNAを導入。デジタルに不慣れなベテランとデジタルネイティブな若手、双方に寄り添うカスタマイズを施し、活用の浸透を進めました。その結果、見えてきたのは、「自分の仕事を俯瞰し、能動的に考える」従業員の意識改革——。
今回は、導入の背景にあった課題からKANNAの活用方法、そして今後の展望まで、工程管理グループのチーフを務める中村晋様、同グループの野口菜々美様にお話を伺いました。
KANNA導入の背景と効果
課題
・Excelによる複雑な工程表の更新作業に時間がかかり、他の業務を圧迫
・情報の即時共有ができず、表の更新と口頭伝達の二度手間に
導入の決め手
・コスト面のハードルを打開する「初期費用なし」で、月額費用も安価
・自社の業務に合わせてノーコードで設定ができるカスタマイズ性の高さ
・導入検討段階から顧客の声に真摯に耳を傾ける手厚いサポート体制
効果・改善
・従業員の仕事の「俯瞰的に見える化」を実現し、能動的な意識を醸成
・日報を手軽な選択式にカスタム。提出が根付き、情報のデータ化も推進
・写真機能により、データの送信・写真の識別・振り分け保存の作業を一掃
お話を伺った方

日本特種ボディー株式会社
工程管理グループ チーフ 生産技術グループ チーフ
中村 晋様
工程管理グループ 野口 菜々美様
需要拡大するキャンピングカー、目下の課題は工程管理の煩雑さ
—— はじめに、御社の事業内容をお教えください。
中村様:キャンピングカーの製造販売を主な事業としています。いすゞ自動車の車両をベースに設計から車内の家具製造まで、すべて自社で行う体制です。また、お客様一人ひとりに応じたカスタマイズ性の高さが当社の最大の強みです。そして、2014年の創業以来、何よりも大切にしているのが安全性の高さ。納品前の細やかな検査はもちろん、安全維持のためのメンテナンスにも対応しています。
レジャーの印象が強いキャンピングカーですが、近年は移動式オフィスや商談スペース、福祉のためのモバイル公共空間として、企業や行政からの需要も増えています災害時の避難拠点としても注目を集め、当社の「EXPEDITIONSTRIKER」はキャンピングカーとして日本で初めて、平時・災害時の双方に価値を持つ「フェーズフリー認証」の認定を受けています。
—— 多方面から需要拡大するキャンピングカーを製造する御社。抱えていた課題をお聞かせください。
中村様:私と野口が担当する工程管理に課題がありました。以前はExcelで管理していましたが、製造業には工程変更が付きものです。特注車両ゆえにカスタマイズの仕様が異なり、単純な表組みでは管理しきれず、表そのものが非常に複雑化していました。
表の複雑さを原因に更新作業に時間がかかり、Excelでは情報の即時共有ができません。情報周知の遅れが現場業務のロスにつながるため、結局は事務所から工場へ足を運び、口頭で伝達してから工程表を更新する、という状態でした。その結果、現場の従業員には「工程表を見ても、それが最新情報とは限らない」という疑念が根付いてしまいました。管理履歴のための表更新は不可欠なのに、口頭伝達も止められない。「口頭伝達と工程表更新」という、もどかしさを伴う二度手間が発生していたんです。

手厚いサポート体制が導入の後押し
—— 工程管理に関わる非効率解消を目的に、KANNAを選ばれた理由とは?
中村様:ずばり、工程表の機能です。これならExcelを用いた工程管理から脱却し、同時にリアルタイム共有も可能になります。また、コスト面も魅力的でしたね。自社向けにシステム開発を依頼すると、初期費用だけでも莫大な費用がかかります。その点、KANNAは初期費用が0円、さらにはランニングコストも良心的なため、社内稟議を通すにも有利に働きました。
カスタマイズ性の高さも決め手の一つです。KANNAを知った当初は「施工管理ツール」として紹介されていたため、製造業である当社にマッチするのか不安もありました。しかし、KANNAは設定も表示項目も細かくカスタマイズできるので、これなら自分たちなりに工夫できると感じました。また、導入検討の問い合わせに対応くださったKANNAのスタッフが非常に親切で、顧客の声に真摯に耳を傾けてくれる手厚いサポート体制も大きな後押しになりました。
若手もベテランも使いこなす スマホで完結する簡単報告機能
—— では、実際にKANNAを導入され、どのように活用されているのでしょうか?
中村様:現場の従業員には「工程表を見ても最新情報は分からない」という意識が根付いていたため、まずは工程表ではなくKANNAの報告機能を入り口に、ツールに慣れてもらうことから始めました。以前は紙の日報を提出してもらっていましたが、これを報告機能に切り替え、電子報告してもらっています。
紙で運用していた当時は日報の内容を集計する時間が取れず、現場の従業員は「その日報、本当に意味あるの?」と感じていたのではないでしょうか。しかし、KANNAの報告機能なら内容が電子保存され、エクスポートもできます。これなら日々の業務報告をデータとして有効活用でき、報告の「意味」を従業員も感じられるはずです。
野口様:私は入社から半年になる新入社員ですが、入社したときはまだ、紙の日報だったんです。正直、「いまだに紙なの!?」と驚いてしまって(笑)。私のようにデジタルネイティブな世代は、ちょっとしたメモもスマホが当たり前です。授業以外、紙に文字を書く機会もあまりなく育ったので、KANNAの報告機能に切り替わったことにホッとしています(笑)。

中村様:野口のような世代がいる一方、デジタルに不慣れな従業員もいます。そのため、何よりも手軽さを最優先にカスタマイズしました。文字入力はさせず、すべての項目がプルダウンの選択式です。これならスマホに不慣れな従業員も、日報の提出を面倒に思う従業員も簡単です。従業員の手を煩わすことのないプルダウン形式の日報が功を奏し、今では皆が日々の報告をしてくれるようになりました。
写真機能も便利ですね。以前は、製造委託していたシェル(居住空間)の引き取りの際、傷がないか担当者が撮影した写真を、管理担当者がメールで受信。受信した写真データを顧客ごとのフォルダに振り分け、保存する手間が発生していました。カスタム前のシェルはどれも似ており識別が難しく、写真管理に無駄な時間がかかっていました。

それがKANNAを活用すれば、当該案件から写真撮影に進むだけで、撮影から保存まで一気に完了。振り分け作業も不要です。写真を撮る担当者は50代後半ですが、活用当初から難なく使いこなしています。担当者自身が便利さを実感しているからこそ、KANNAの活用が根付いています。
作業者が実績を登録し、自らの仕事を俯瞰するための第一歩に
—— 導入のきっかけにもなった、工程表についてはいかがですか?
中村様:まだまだ試行錯誤の段階ではありますが、「車両単位」と「お客様単位」という2種類のテンプレートを作成し、全体の工程管理をしています。「車両単位」には、管理担当である私や野口が計画段階の工程スケジュールを登録。一方、「お客様単位」には、1工程にかかった日数など、その実績を現場の従業員に登録してもらっています。
計画を登録するテンプレートと実績を登録するテンプレートを分けた理由は、従業員の意識を変えるためです。従業員自らが業務実績を登録することで、1工程の作業にどれくらいの時間がかかっているのか、自分の仕事を俯瞰的に見られるようになります。その結果、作業時間を短縮するにはどんな工夫が必要か、上司の指示を待たず、能動的に考えられるようになるはずです。
現在はExcelからKANNAへの移行期間として、Excelの更新と口頭での変更周知も続けています。しかし、KANNAの活用が浸透するにつれ、「スケジュールは人に聞かず、自分で工程表を確認」という意識が根付いていくと信じています。従業員一人ひとりに実績を登録させているのは、自分の仕事を俯瞰的に見る習慣を付けると同時に、KANNAに触れる機会を意図的に増やすためでもあるのです。
若手定着にデジタル化は必須。熟練の技術と感性を融合させるDX
—— それでは最後に今後への期待と合わせ、御社と同じように業務のDXを目指す他社にメッセージをお願いいたします。
中村様:期待としては、やはり従業員の能動的な意識が高まることです。私たち管理担当者が知る情報には限りがあり、製造のことを熟知するのは現場の従業員です。従業員一人ひとりが自らの仕事を俯瞰的に見つめ、「ここはもっと改善できるな」と能動的に考えられることが、私たちが目指す理想の在り方です。そして、その意見に耳を傾け、より効率的な作業工程を考えることが、私たち管理担当者の本来の使命だと考えています。
KANNAには期待を抱けるだけのポテンシャルがあります。将来的には、製造工程だけでなく顧客管理にもKANNAを活用し、情報を一元化したいと考えているところです。現在、工程管理と顧客管理は、部署も情報管理の手段も分断しています。顧客データが必要になるたびに担当部署に問い合わせていますが、双方を一元管理できれば、情報の「引き出し」が一つにまとまり、スムーズに確認できるようになります。
野口様:KANNAは情報の引き出し。本当にその通りだと実感しています。今、当社はベトナム工場の開設を進めており、サポート役の中村が長期出張に出てしまいます。最初に聞いたときは「私の指導役はどうなっちゃうの!?」と戸惑いました(笑)。でも、KANNAがあれば安心です。KANNAに登録された過去の情報を参考にすれば、海外にいる上司に逐一問い合わせなくても工程の組み立てができます。

中村様:問い合わせず、自分で解決する。まさにこれが、私たちの理想の在り方です。すべての従業員がこの理想形にたどり着くには時間が必要ですが、KANNAのスタッフは本当に心強い存在です。業務効率化やDXに頭を悩ませている他社の方も多いと思いますが、KANNAのスタッフは私たちの考えに真摯に耳を傾け、どのような活用方法やカスタマイズが適切か、常に一緒に考えてくれます。
また、製造業全体が人手不足という課題を抱える今、私たちは若手が「働きやすい」環境をしっかりと考えなくてはいけません。若手にとってデジタルは当たり前です。アナログな方法に固執していては、将来的な入社も望めません。デジタルに不慣れな従業員への配慮と同時に、若手の働く基盤を作る必要があります。その点、KANNAはカスタマイズ性の高さと手厚いサポートにより、地に足の着いた、持続可能なDXを進めることができるのです。
記事掲載日:2025年10月23日