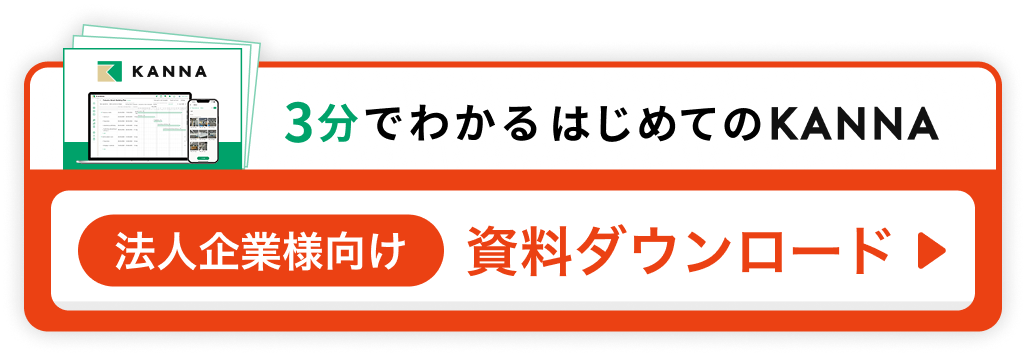「責任の分散化」へ。土木現場が変わる、自治体の業務効率化

��オフィス街、観光地、高級住宅街、そして各国の大使館が集まるグローバルな街。あらゆる顔を持つ東京・港区。その安全・安心な暮らしを下支えするインフラを担うのが、今回お話を伺った「麻布地区総合支所 まちづくり課」です。
いつ起こるかわからない自然災害やゲリラ豪雨。刻々と変わる現場の状況をリアルタイムで共有し、迅速に対応すること。それが、区民の命を守る自治体の責務です。一方で、全国の自治体が人手不足に悩む中、アナログな情報共有や非効率な業務体制は、職員の負担を増大させかねません。
年間600件もの突発案件に対応するなかで抱えていたのは、「電話とメールによる伝言ゲーム」というコミュニケーションの課題。そして、「情報が分散し、引き継ぎが難しい」という情報管理の課題でした。なぜ、港区は「KANNA」の実証実験を決めたのか。麻布地区総合支所 まちづくり課の飯塚様、八木様に、その背景にある課題から、KANNAがもたらす効果と働き方の未来についてお話を伺いました。
KANNA導入の背景と効果
課題
・複雑な連絡体制:関係者が多く、電話とメールによる伝言ゲーム状態。情報のタイムロスや認識のズレが頻繁に発生
・データ保管の限界:サーバーの容量制限により、案件ごとの写真や図面をすべて電子保存することが困難。必要な情報が分散
・引き継ぎの非効率:過去の資料やメールが残せないため、異動のたびに引き継ぎが難航
導入の決め手
・複数のツールを組み合わせるのではなく、現場で使うスマートフォンで「ワンストップ」で利用できる点
・直感的でわかりやすいインターフェースに、「これなら使える!」と確信
効果・改善
・情報をリアルタイムに一元共有:仲介者を経由せずに同一情報を一斉共有でき、迅速対応を後押し
・視認性の高い資料保管:情報を案件ごとに見やすく保管、大容量クラウドにより容量制限も払拭
・情報蓄積による引き継ぎの円滑化:チャットの内容も網羅的に蓄積され、過去の業務工程を可視化
お話を伺った方

港区 麻布地区総合支所 まちづくり課
土木担当係長 飯塚陽子様
まちづくり係 八木脩太様
国際都市・港区の安全・安心を支える土木インフラの維持管理
—— はじめに港区について、また、KANNAの実証実験をされる「まちづくり課」についてお聞かせください。
飯塚様:港区は非常に多様性に富んだ地域です。皆さんが思い浮かべるように国際的な顔を持つ一方で、2023年の調査(※)では、区の総人口の約7.9%にあたる約2万1000人の外国人が住み、その国籍は130カ国にも及びます。また、港区には芝、麻布、赤坂、高輪、芝浦・港南の5つのエリアがあり、自治体としてもそれぞれに支所を設けています。例えば、芝浦・港南はタワーマンションが建ち並ぶ子育て世代が多いエリア。赤坂はオフィス街です。私と八木が勤務する麻布は、古くからの住宅街、六本木に象徴される繁華街、そして数十カ国の大使館が集まるグローバルな一面が混在する、特に多様性に富んだエリアです。

八木様:まちづくり課では、道路や河川、橋梁、公園といった区内の土木施設の整備と維持管理を担っています。整備は橋の架け替えや電線の地中化といった大規模な工事、維持管理は施設のメンテナンスや小規模な修繕を指しますが、担当する案件数は膨大です。職員1人あたり常時5〜6案件を同時並行で担当し、現場の実務を担う協力会社の方々と連携しながら業務を進めています。

※港区国際化推進プラン https://www.city.minato.tokyo.jp/documents/7372/japanese_plan.pdf
年間600件の突発案件。非効率な電話とメールの「伝言ゲーム」
—— 港区のまちづくり課では、どのような課題を抱えているのでしょうか?
飯塚様:職員一人ひとりが抱える案件数の多さに加え、1案件ごとの関係者数も多く、各自への連絡がスムーズにいかないことが課題の一つです。例えば、港区では「指定管理者制度」という仕組みを導入し、公園の管理を民間業者に委託していますが、区民の多くは「公園の管理をするのは自治体」という認識をお持ちのため、遊具の故障や園路の破損といったトラブルが生じても指定管理業者ではなく、私たち自治体のもとに修理の要望が入ります。
区民の方から要望を受けた後、私たちはすぐに協力会社の所長へ電話かメールで内容を共有します。しかし、電話では所長が不在だったり、メールの確認に時間がかかったりすることも少なくありません。さらに、実際の作業は所長ではなく、担当者の方々が行います。つまり、私たちが所長に伝えた内容を、所長が各担当者に伝えるという「伝言ゲーム」状態。これでは時間がかかるうえに、情報が正確に伝わらないこともありました。
また、写真や図面の共有にも苦労していました。区民の皆さんの情報を守るため、自治体のメールシステムには厳重なセキュリティがかけられており、メールに添付できるファイルの容量が限られています。そのため、1案件の資料を共有するために、5つに分割して5件のメールを送らなければならないことも。送る側も受け取る側も、非常に手間のかかる状態でした。
こうしたファイル容量の制限は、資料の保管にも影響を及ぼします。港区ではペーパーレス化を推進する一方、自治体のサーバーに保管できる容量にも限りがあり、一から十まで、すべての資料を電子保存することは非現実的です。できることなら関係者とのメール履歴も逐一残し、いつでも見返せるようにしたい。しかし、年間計画に組み込まれた工事やメンテナンスに加え、先ほどもお話しした公園の設備修理のような突発案件が次々と発生し、それだけでも年間約600件。平均すると月50件、日に1〜2件の突発案件が発生する計算です。
計画案件も突発で起こる案件も、案件ごとの詳細を記録した指示書という書類を作成していますが、小規模案件の指示書まで電子保管していては、すぐにサーバーが満杯になってしまいます。これはメールも同様に過去の履歴まで逐一残すことは難しく、すると職員の異動や退職による引き継ぎの際に支障が生じます。過去に似たような案件があっても当時の指示書やメールが残っておらず、職員は参考となるサンプルなしに、また1から業務を進めなくてはなりません。
八木様:引き継ぎの難しさは自治体職員だけでなく、連携する民間業者の負担にもなります。退職した職員のメールアカウントはすぐに削除するため、直近のメールのやり取りも確認できません。これは私が実際に経験したことですが、工事を発注している協力会社の方に写真資料を求めたところ、「すでに送っています」という返答でした。しかし、その写真を受信したのは前任者で、引き継いだ私の手元にはありません。協力会社の方には二度手間になるため、「申し訳ないのですが、もう一度送っていただけますか…」と恐縮しながら再送をお願いしたこともあります(苦笑)。
飯塚様:特に異動した当初は本当に大変です。職員は異動間もなく、土木のプロである協力会社の方々と対等に業務を進めていかなくてはなりません。近年は全国の自治体で人手不足が深刻化しており、職員一人ひとりの負担が増えるほど離職率も高まります。こうした課題を解決するためにも、KANNAのようなDXツールが必要でした。この積極的なDX推進は、区長の意向でもあります。
決め手は現場に寄り添う直感的な操作性
—— 課題解決に向けた実証実験のDXツールに、KANNAを選ばれた理由をお聞かせください。
八木様:きっかけは、港区の職員向けに開催されたDX展示会です。10社ほどの企業が参加されていましたが、土木関連に役立つサービスがあるのか、最初は不安でした。しかし、KANNAのブースで話を聞いたとき、「これなら伝言ゲーム状態の連絡体制から脱却できる!」と直感的に感じました。事務や人事向けのパソコン専用ツールばかりだろうと思っていましたが、KANNAはスマートフォンでも使える。現場での業務が基本の私たちにとって、うれしい誤算でしたね。

飯塚様:八木からKANNAの説明を聞いて、私としては「やっと求めていたツールに出合えた!」という気持ちでした(笑)。業務効率化のシステムやツールがあることは知っていましたが、私も八木と同様、土木業務との親和性に不安を感じていたんです。しかし、KANNAなら複数の関係者とワンストップで連絡ができ、資料のクラウド管理も、案件カレンダーを使った進捗管理もできる。Excelでの進捗管理では更新に苦労していたので、足元の課題から業務全体の効率化まで、幅広く期待を持てたことがKANNAを選んだ決め手です。
災害への初動対応を「組織」で。DXが実現する働き方改革と「責任の分散化」
—— 間もなく始まるKANNAの実証実験。具体的に、どのような効果を期待されていますか?
八木様:情報の一元共有によるワンストップの連絡体制には、大きな期待を寄せています。現状、メールのCCで関係者に情報を共有していますが、大量のメールに埋もれたり、他の案件の情報と混同したりすることがよくありました。KANNAなら業務連絡や資料が案件ごとに整理され、プッシュ通知も来るため、情報の見落としや混同がなく、すぐに確認できるようになります。
飯塚様:情報を迅速に取得し、スピーディーに共有することは、今、私たち自治体に非常に求められています。昭和や平成初期に造られた設備が老朽化し、全国で道路の陥没といった事故が増加しています。また、近年はゲリラ豪雨も頻発し、最悪の場合、区民の命に関わる事態にもなりかねません。
こうした緊急事態にいち早く対応するには、現場の状況把握と共有が不可欠です。KANNAなら誰かが撮影した写真を投稿するだけで、関係者全員が同じ情報を即座に確認できます。さらに、チャットでリアルタイムにやり取りができるため、迅速な対応が可能になります。
八木様:計画案件も突発案件も、どんな対応をしたのか、連絡の履歴も資料も、すべてがKANNAのクラウド上に蓄積されます。これは引き継ぎの難しさを解消すると同時に、ペーパーレス化も推進できます。また、案件カレンダーの機能にも期待しています。各自が担当する案件の進捗状況が一覧で可視化されるため、担当者だけでなく、全案件を管理する職員も状況把握がしやすくなります。

飯塚様:リアルタイムの情報共有、情報の蓄積、進捗状況の可視化は、すべて「業務の見える化」につながり、それは「組織としての業務遂行」につながるのではないでしょうか。土木設備にしても公園にしても、深夜や休日にトラブルが発生することもあります。
その先に目指すのは、業務効率化だけではありません。自治体職員の働き方改革です。当課では2025年10月からKANNAの実証実験を始めますが、この背景には、行政専用ネットワークLGWANを経由しないパソコンが支給されることがあります。LGWANはセキュリティレベルが高いため、外部サービスの導入ハードルが高く、KANNAのようなDXツールを取り入れられずにいました。しかし、区として積極的にDXを推進するという意思決定のもと、今後はLGWANへの接続を停止し、高セキュリティなツールに限り導入が可能になります。
港区では以前からテレワークを推進していましたが、ネット接続や緊急対応の難しさがネックで、なかなか実現できませんでした。KANNAの実証実験をきっかけに業務効率化が進み、場所を問わない働き方が実現できれば、職員一人ひとりの負担軽減につながります。さらに、業務効率化は人件費削減、ひいては財源確保にもつながります。自治体の財源は税金のため、これは区民の皆さんのためにも非常に重要です。
DXは「責任の分散化」と「組織力の最大化」をもたらす
—— それでは最後に、業務効率化に向けたDXを考える他の自治体へメッセージをお願いします。
飯塚様:自治体の財源は税金であり、DXの推進には費用対効果を慎重に見極める必要があります。「もし効果が出なかったらどうしよう…」と不安に感じる職員の方は多いはずです。特に土木のDXはイメージがつきにくく、事務管理のDXよりもコストがかかる印象があるかもしれません。しかし、KANNAは大きなシステムや機械を導入するわけではなく、ツール自体も手軽でコストも比較的安価です。パソコンではブラウザで、スマートフォンやタブレットではアプリをインストールするだけで使えます。
KANNAは災害対応にも適したツールです。区民の生活を守るため、一刻も早い災害対応は自治体としての責務ですが、責任が重く、業務的にも精神的にも負担が大きくなります。そんなとき、関係者とスムーズに連携が取れるKANNAは、いい意味での「責任の分散化」をもたらします。発災の初動段階から関係者全員が情報を共有し、チーム一丸となって対応できる。つまり、責任の分散化が職員一人ひとりの負担を軽減しながら対応を迅速化し、自治体という組織全体の力を最大化できるのではないでしょうか。
記事掲載日:2025年09月30日