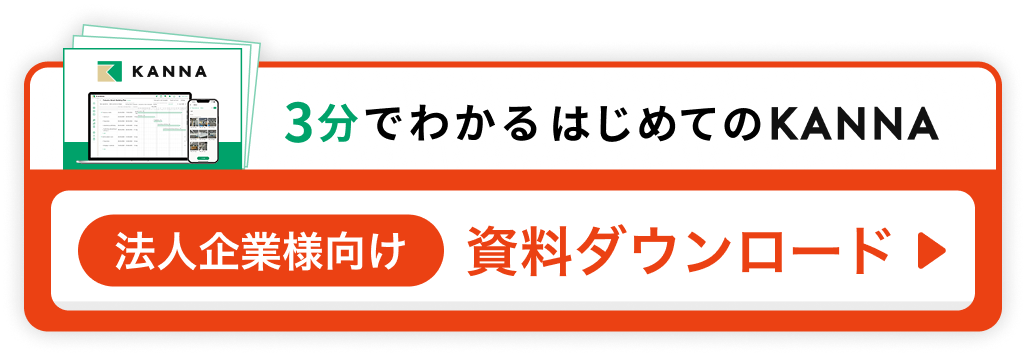切手代・収入印紙代を大幅削減。「取適法」施行を前に、アナログ帳票の郵送文化を一掃


会社名
株式会社クマヒラ
従業員数
764名(2025年4月1日時点)
事業内容
セキュリティシステム 金融機関向け設備 空間プランニング 文化財設備 原子力設備
活用サービス
創業120余年の歴史を持ち、セキュリティソリューションで国内トップクラスのシェアを誇る株式会社クマヒラ。金融機関向け設備やセキュリティシステム、特殊扉、文化財保存設備まで、人々の安全・安心に大きく貢献しています。
施工・保守を担う協力会社との連携には、迅速かつ確実な情報共有が不可欠です。しかし、メールでは「言った、言わない」の齟齬や確認漏れが発生し、請求書などの重要帳票は郵送という長年の慣習により、コストと時間のロスが常態化していました。
2026年1月の「取適法」施行を控え、コンプライアンス強化が求められる今、帳票運用のスピードを上げることも喫緊の課題。今回は、課題解決のツールにKANNAを選んだ理由から運用方法、導入効果から今後の展望まで、KANNAの導入を牽引され、活用浸透にも尽力される、同社技術部の榎健様、小久保喬裕様、高橋遼成様にお話を伺いました。
KANNA導入の背景と効果
課題
・メール連絡による「言った、言わない」の齟齬が発生
・使用する連絡ツールが協力会社ごとに異なり、情報抽出に手間と時間がかかる
・やり取りが個人の端末に限定され、属人化の原因に
・郵送による帳票のやり取りがタイムロス、切手代や収入印紙のコスト負担に
導入の決め手
・基幹システムと連携可能な高いカスタマイズ性
・IPアドレスの制限など厳しい条件をクリアしたセキュリティレベルの高さ
・帳票の作成・提出・受領をすべて電子化できるKANNAレポートの機能
・誰でも迷わず操作できる直感的なユーザーインターフェース
効果・改善
・資料共有も関係者全員に情報周知でき、属人化を解消
・チャットの既読機能で、確認電話が激減
・大容量ファイルも手間なく共有でき、外部ストレージサービスが不要に
・帳票をKANNAレポートに移行し、タイムロスと同時に郵送・印紙のコストも削減
お話を伺った方

株式会社クマヒラ
技術本部 技術部 次長 榎 健様
関東支社 技術部 さいたま駐在 課長 小久保 喬裕様
技術本部 技術部 管理課 主任 高橋遼成様
セキュリティの大手が抱えていた「情報共有」と「郵送文化」の課題
—— はじめに、御社の事業内容をお教えください。
榎様:セキュリティシステム、金庫・保管保存設備、プランニング・デザイン、文化財保存設備、特殊扉といった、セキュリティ関連サービスや機器を手がけています。私たちは1898年の創業から120年以上の歴史を持ち、セキュリティソリューションにおいては国トップクラスのシェアをいただいています。創業時から積み上げた技術力はもちろん、お客様の財産を守るプロとしての自覚を胸に国産金庫開発をリードし、現在は入退室管理システムやセキュリティゲートに象徴されるトータルセキュリティ企業として、お客様の安全・安心に寄与しています。

グループ会社である熊平製作所と連携し、開発・製造から施工、保守・メンテナンスまで、トータルに対応できる点も私たちの大きな強みです。特に弊社は全国各地に支店や営業所を設け、地域のお客様をきめ細かくサポートしています。その中で、KANNAを導入したのは、システムや機器の施工・保守・修理を手掛ける技術部です。デジタル技術を駆使したセキュリティシステムから、お客様の財産をフィジカルにお守りする金庫・保管保存設備や特殊扉まで、幅広い分野の対応に当たっています。

—— 現場との連携において、具体的にどのような課題をお持ちでしたか?
小久保様:施工や保守、修理といった現場業務を担当いただく協力会社との連携に、大きな課題を抱えていました。例えば、施工の核となる図面は、クライアントとの打ち合わせのたびに更新されます。その都度、協力会社の方々に最新の図面を共有する必要がありますが、KANNA導入前の共有手段はメールでした。
メールでは先方からの返信がない限り、相手が内容を把握したのか確信が持てません。また、他のメールに埋もれて確認漏れが生じたり、誤って削除されてしまったりすることもありました。図面更新が頻繁にあると、現場を管理する弊社側にも、最新情報を共有したつもりで送信しそびれるといったミスが発生していました。
精度の高い施工のため、協力会社の方に現場の写真を送っていただくこともありますが、メールで送られてきたり、ショートメールで送られてきたりと、手段が統一されないことも課題でした。情報確認のためにメールとショートメールの履歴を行き来する小さな手間が積み重なり、結果的に全体のリードタイムに影響を及ぼしていたのです。

榎様:さらには、情報の属人化という課題も生じていました。メールやショートメールでのやり取りでは、情報が担当者のアカウントやスマートフォンに閉じてしまうため、部署全体で共有できません。結果的に情報が属人化し、担当者が不在となるとスピーディーな対応が困難になっていました。
迅速な対応が求められるのは、協力会社へのお支払いについても同様です。2026年1月に「下請法」が「取適法」へと改正され、コンプライアンスの強化が求められる今、一切の遅延なくお支払いをするのは弊社の社会的責務です。しかし、KANNA導入前は、請求書や領収書といった帳票のやり取りを郵送で行っていました。アナログな郵送では書類の到着までに時間がかかり、お支払いの遅延につながりかねない状況でした。この帳票運用のスピード感の改善も、KANNAを導入した理由の一つです。

「郵送と決別できる」、確信させたKANNAレポート
—— 確実な情報共有や属人化の解消、帳票の迅速なやり取りを実現するためのツールとして、KANNAを選ばれた理由とは?
榎様:私たちの業務は、一言でいえば施工管理です。施工管理の業務効率化を目的にDXツールを模索していたところ、KANNAにたどり着きました。他にもいくつかの類似サービスと比較検討しましたが、KANNAはカスタマイズ性が圧倒的に優れていました。案件ごとの進捗を示す項目名もノーコードで簡単かつ自由に書き換えられるため、弊社の基幹システムに合わせた柔軟な運用が可能だと判断しました。
また、KANNAはセキュリティレベルの高さも抜きん出ていました。弊社の事業は、お客様の大切な財産と安全・安心をお守りすること。情報漏洩は絶対にあってはならず、外部サービス導入には非常に厳しい条件を設けていますが、IPアドレスの制限をはじめ、KANNAは弊社が設けたすべての条件をクリアしていました。
機能面では、私たちが求めていた要素が網羅されていました。図面や写真といった資料も、チャットによる連絡周知も、案件ごとに一元共有できます。招待した関係者全員が同一の情報を確認できるため、属人化の解消につながると考えました。そして、特に惹かれたのがKANNAレポートの機能です。業務に関わる帳票すべてを電子化でき、提出も受領もKANNA上で完結できます。これなら、長年の課題であったアナログな郵送と決別できると確信しました。
導入検討に当たり、カスタマイズ性やセキュリティレベルの他にも複数の検討項目を立て、他社のサービスと比較しましたが、最終的な決め手は直感的に操作できるUIです。弊社の従業員にも協力会社の皆さんにも使ってもらえなければ、導入しても意味がありません。操作が難しくてはツールも浸透しませんが、KANNAなら「いける」と思えたことが最後の一押しになりました。
紙の注文書類のやり取りを電子化、郵送コストと印紙代を大幅削減
—— では、実際にKANNAを導入され、どのような効果を実感されていますか?
小久保様:資料の「送った、送っていない」、情報の「言った、言わない」といった齟齬が解消されたことが、一番大きいですね。情報の一元共有ができるKANNAだからこそ得られた効果です。KANNAはチャットと資料フォルダの紐付けができるため、チャットに資料を投稿すれば、それだけで指定フォルダへの保存も完了します。管理者である私の立場からすると、送付と保存が一度に済むのは非常に効率的です。協力会社の方々からすれば、情報をタイムリーに受け取れると同時に、いつでもどこでも必要な情報を見返すことができます。

チャットには既読機能があるため、「送った資料、確認いただけただろうか?」という不安も解消され、確認のための電話をかける頻度も、受ける頻度も激減しました。以前は、資料の確認のために電話をかけたり、協力会社の方から施工方法の確認電話をいただいたりすることが多かったのですが、今ではKANNAのチャットで完結しています。チャットなら写真の投稿もできるため、電話での口頭説明よりも解像度高く現場の状況が把握でき、明確な指示を出せるようになりました。
電話が完全になくなったわけではありませんが、KANNAのチャットに投稿された写真を見ながら、電話で口頭説明を受けることも可能です。以前は「写真をショートメールで送りました」と言われても、スマートフォンの画面を見ながら会話をするにはイヤホンをするかスピーカーに切り替えるしかなく、ちょっとした手間でした。今はその手間も解消され、パソコンのブラウザでKANNAを開けば、写真を見ながらスムーズに会話できます。投稿された写真が記録として残る点も大きなメリットです。
また、大容量ファイルのやり取りも効率化しました。弊社が取り扱うセキュリティシステムのファームウェア更新に必要なプログラムはサイズが大きく、以前は外部のストレージサービスを利用して共有していましたが、今はKANNAに投稿するだけです。パスワードの設定やメールの作成も不要になり、「このプログラムを誰に送るべきか」という選定も必要ありません。本当に楽になりました。
高橋様:KANNAの導入効果は、情報共有だけでなく、帳票のやり取りにも劇的に表れています。着工から完工、お支払いまでに必要な見積書、注文書、請書、請求書、領収書といった帳票をすべて電子化したのはもちろん、運用の流れもKANNAの活用を前提とした形に改めました。具体的には、案件の立ち上げと同時にKANNAのチャットに協力会社への依頼業務内容を投稿します。協力会社の方はその内容を元にKANNAレポートで見積書を作成し、弊社の担当者は見積書を確認した後、承認フロー機能で「承認」「差し戻し」の通知を行います。
その後、承認済みの見積書を元に注文書を発行し、先方から請書をいただく流れですが、請書の提出と合わせ、KANNAの報告機能に着工日や受注金額を登録いただいています。

榎様:その結果、帳票のやり取りにかかる時間が圧倒的に削減されました。郵送していた当時は、書類に不備があると訂正後の帳票を受け取るまでにさらなるタイムロスが発生し、たいへんな手間でした(苦笑)。さらに、郵送では1通ごとに切手代が発生するだけでなく、請書や領収書には収入印紙も必要です。帳票をすべて電子化したことで、切手代も収入印紙代も一気になくなったのですから、弊社だけでなく、協力会社の方々の負担も間違いなく軽減されたはずです。

無理なく確実な活用浸透に向け、運用マニュアルを作成
—— さまざまな導入効果を実感されていますが、KANNAの活用を浸透させるためのお取り組みをされたのでしょうか?
榎様:弊社に最適なKANNAの運用方法を探るため、一気に全国展開するのではなく、まずは本店営業部・関東支社の2拠点に絞ったスモールスタートの形を採りました。KANNAは直感的に操作できますが、デジタルに不慣れな従業員や協力会社の方々にも積極的に活用してもらうため、全国展開の前に実際の使用感や運用方法に関する意見を吸い上げ、無理なく業務効率化を進められる体制を整えました。
スモールスタートから約3カ月後に全国展開を開始しましたが、それまでに弊社の従業員向け、協力会社向けのそれぞれ100ページにのぼるKANNAの運用マニュアルを作成しました。KANNAのお知らせ機能にマニュアルへのリンクを張り、操作や運用に迷ったときにすぐに確認できるようにしています。このマニュアルを作成したのが高橋。高橋はKANNAのプロです(笑)。
高橋様:KANNAは頻繁に新しい機能が追加されるので、私自身も追いつくのが大変なくらいです(笑)。しかし、新機能がリリースされるたびにまずは試し、さらなる業務効率化につなげるようにしています。とはいえ、文章とフローチャートのみのマニュアルでは、取っ付きづらさを感じる人もいるかもしれません。そこで、新たに操作方法を動画にまとめたマニュアルの製作を進めているところです。

榎様:動画マニュアルの作成には、以前から導入していた外部のオンラインサービスを活用しています。このサービスは導入から5年ほど経っていましたが、当時は利用が根付かず形骸化していました。弊社はKANNAの活用浸透と並行して基幹システムの刷新も進めており、このタイミングを一つの転機と捉えています。KANNAはもちろん、すでに導入している他のサービスもしっかりと活用し、全社的な業務効率化につなげようと考えています。
小久保様:マニュアルによるサポートはもちろんですが、ツールやサービスを根付かせるには、活用する人一人ひとりが効果を実感することが何よりも大切です。私もKANNAの活用を推進する立場として、現場の担当者にも協力会社の方々にも「使ったら楽になりますから」と積極的に伝えています。KANNAには新たにタスク機能もリリースされましたが、これもまずは私自身が率先して活用し、その便利さを伝える旗振り役にならなくてはいけないと思っています。
KANNAの活用アイデアを標準化し、さらなる業務効率化へ
—— では、今後もKANNAをご活用いただき、どのような業務体制を目指すのか、展望をお聞かせください。
榎様:お話ししたように、KANNAの導入効果は明らかです。現在は全国の支店ごとに活用の浸透度に差がありますが、しっかりと活用している支店は業務効率化を実感し、さらに積極活用するという好循環が生まれています。この効果が評価され、修理を専門とする部署からも「KANNAを導入したい」という声が上がり、来期からの運用を計画しています。
部署ごとに業務の進め方が異なると連携が取りづらく、ミスも起こりやすくなるため、全社横断的なツールの標準化は非常に重要です。技術部内はもちろん、他部署にもKANNAの活用が浸透したなら、各支店、各部署から新たな活用方法のアイデアが生まれることでしょう。実際、積極的に活用する中四国支社では、協力会社の差配を目的にカレンダー機能の活用を始めています。私たちは、各所から届く活用のアイデアを順次標準化させ、業務に関わる全員が効率化を実感できる体制を整えていきます。
記事掲載日:2025年11月19日